~unreasonable woman~
「成金のお嬢様って、本当にワガママなんですね。他人のものを取ることも、悪気なんてないのかしら?」
トイレから出た途端、そんな言葉をふっかけられ、体が硬直した。
あからさまな悪意と毒のある台詞。
正面に立つその女は、初めて見る表情でこちらを見下ろしていた。
・
・
清四郎の気持ちが………自分のものになった夜。
雨の中、それでも酔っ払いが練り歩く街に、あの後直ぐ、魅録のジープがやってきた。
濡れたアスファルトに水しぶきをあげ、大通りの端っこにハザードランプで停車する。
「よっ。早かったろ?」
「済みませんね………こんな遅くに呼び出して。」
さっきのメールはどうやらこれだったらしい。
二人の男は示し合わせたように挨拶した。。
「なんで魅録?」
「は?清四郎に言えよ。俺はハイヤー代わりに来てやったんだぞ。」
突き放すようにそう言われ、思わず清四郎を見上げると、雨に濡れた前髪をかきあげたヤツはバツ悪そうに笑っていた。
「どういうこと?」
苦笑する顔は本当に困ったような表情で、でもその意味は全く読めない。
なんで?
今夜は二人で話す夜なんじゃないの?
せっかく両想いだって解ったのに。
なんで?
雨の中、刻まれた腕の熱さが徐々に冷えてゆく。
魅録が楽しげに話しかけてくるのに、ちっとも応えられない。
────なんで?
そっと距離を縮めた清四郎は、あたいの耳元に唇を寄せてきた。
互いの想いを知ったばかり。
あれは夢でも幻でもない。
甘い吐息と情熱的な告白。
心に奥に触れた………初めての男。
熱くて身悶える記憶が自然と呼び覚まされる。
「タクシーだと………どうしてもホテルに連れ込みたくなるんでね。ここは誰よりも信頼できる彼に任せます。」
「なっ………何言ってんだよ!バカ!」
頭が軽く沸騰する。
こんな言葉がヤツの口から出るなんて信じられない。
魅録の前だぞ?
どーすんだ!?
「今日は少し飲み過ぎました。だから………無事に帰してやりますよ。」
小声でそんなこと言われても、どう切り返していいのか分からない。
好きだと…………愛してると言われたのはほんの五分前だ。
実感だって湧かないのに。
清四郎はそっと耳に触れ、こちらがのぼせるような声で「次は………覚悟して下さい」と宣言した。
次?
次って……………何?
結局、魅録は何も尋ねることなく、家まで送り届けてくれた。
二人が楽しそうに語り合っていたから、割り込む余地も無かった。
ちょっぴり寂しいと思ったけど、仕方なくさよならをした。
恐らく二人は、清四郎ん家で話の続きをするのだろう。
もしかすると、あたいたちのことかもしれない。
その夜は直ぐ、ベッドに潜り込んだ。
未だかつて経験したことのない、甘酸っぱい切なさと共に。
それでも────
“愛してる”と言った、清四郎の真剣な声を反芻していると、いつの間にか優しい夢に誘われていった。
幸せな夢にほんの少しの不安を落として。
清四郎─────ほんとに、ほんとだよね?
信じていいんだよね?
・
・
次の日は朝早くからメールが届く。
『おはよう。よく眠れましたかな?今日は昼飯でも一緒しませんか?』
忙しいくせに───
まるでこっちの気持ちを見透かしたかのようなタイミングだ。
当然『O.K.』の返事を送り、汗くさい体をシャワーで流す。
その日はみっちり講義が入っていて、特に午前の二コマは小うるさい教授が教鞭を振るう為、遅れるわけにはいかなかった。
新しい色のバスローブに身を包み、歯を磨いていると、平らな胸元につい目が留まる。
男と間違われる躰。
色気もくそもない。
清四郎だってそう言ってたじゃないか。
少年のような………身体だと。
コンプレックスをそこまで意識したことは無かった。
ほかの誰と比べることも少なかった。
自分に自信があったし、恋なんかしないと信じてたから。
でも清四郎の言葉に意識されられ、何もかもが気になり始めた。
頭の悪さ
雑で下品な行動
女らしくない身体
あのプライドの高い男が好きになる相手は、完璧な女だと予感してたのに、諦めることも出来ないまま、親しい友人のポジションに居座る自分が情けなかった。
“東英”という女が現れて、いよいよ輪郭を見せ始めた気持ちは膨らむのも早く、押し殺すには相当苦労した。
清四郎が選ぶのは、野梨子や可憐のように魅力ある女だ。
けして、彼女のようなタイプじゃあない。
誰よりも納得できなかったのは野梨子でなく、あたいだ。
そりゃあ、打算で婚約しちゃうような酷い男だけど────
ヤツが恋する相手はもっとイイ女のはずだろう?
そう信じながらも、周りをうろつく女にイライラさせられていた。
今から考えるとそれは醜い嫉妬で、自分には到底出来ない清四郎へのアプローチをやってのける彼女が少し羨ましかったのかもしれない。
磨き終わった後の唇にそっと触れる。
────キスしちゃったんだ。
雨の中で、あの時感じた高揚は例えようもない。
清四郎の吐息。
清四郎の視線。
清四郎が持つ………男の香り。
明らかに興奮していた。
その渦に巻き込まれそうだったから。
優しい包容の中で、あたいは確かに欲情していたんだ。
だからどうなってもいいと思っていた。
誘われたら断れない。
清四郎に求められたら、絶対喜んでしまう。
だからこそ魅録の登場が残念だった。
「やらしいぞ、あたい!」
顔をパンと両手で叩く。
頭ん中がヘタクソな妄想に占領されそうだ。
清四郎
清四郎
あたい、こんなにもおまえのことが好きだ。
恋がすべてを変える。
いつか可憐が言ってた言葉。
“女は恋すれば自然と可愛く、美しくなるものよ”
……………それって、あたいにも通用する?
変われるってこと?
それなら清四郎の望むような女になりたい。
ずっと側に居たいから。
幻滅されたくないから。
こんな考え、ちっとも自分らしくないけど、清四郎がくれた想いを絶対に捨てたくはない。
絶対に。
・
・
・
その日のランチは二人きり───だったはずなのに、美童や可憐、最終的に野梨子と魅録も加わり、いつものメンバーが揃ってしまった。
当然、可憐は追及してくる。
夕べのことを。
案の定口ごもるあたいに代わって、清四郎は堂々と交際宣言をかます。
「やったじゃない!悠理。」
「俺は夕べ聞いたぜ。ま、驚いたけどよ、収まるとこに収まったって感じだよな。」
「悠理と清四郎かぁ。当たり前のようでいて………なーんか色気足りないんだよねぇ。それにいいの?こわーい小姑がここに一人いるけど。」
「失礼ですわ、美童。わたくしとしては、清四郎が悠理を愛しているなら何ら問題ありませんの。以前のような打算的な関係なんて、絶対に認めたくありませんから。」
難関だったはずの野梨子のゴーサインに、背中が武者震いする。
簡単すぎる納得と皆の祝福は、それでも心をあったかくしてくれた。
「ちゃんと………今度はちゃんと、僕の想いを伝えましたよ。」
清四郎に見つめられ、胸はドキドキ。
みんなの手前、思わず目を逸らす。
「あたし、清四郎って一生恋愛出来ないと思ってたけど違ったのね。 ………そう考えたら、悠理ってすごいわぁ。」
感心しながらも、可憐は複雑な顔を見せた。
「あたいだって………何が何やら。あんだけ馬鹿にされ続けてきたんだ。さすがに………びっくりしたよ。」
「まあ、いいじゃねぇか。誰もが羨むトップクラスの男を手に入れたんだ。胸張っとけ?」
「あら、悠理だってトップクラスの女の子ですわよね?美人で大金持ち。ただちょっとオツムが足りないだけで。」
「イヤミくせーぞ、野梨子!やっぱあたいが清四郎とつき合うのヤなんだろ?」
「ほほ、小姑扱いされたんですもの。このくらいの意地悪、当然ですわ。」
テラスに笑い声が広がる。
その時のカフェテリアは満員御礼だった。
だからそこに、東英静香の取り巻きが1人くらい居ても、ちっともおかしくはなかったんだ。
その翌日────つまり今日。
あたいの前に仁王立ちする女の顔はまさに般若だった。
緩やかな、肩までのウェーブへアを耳にかけ、今流行りのファッションに身を包む。
ヒールの所為か、目線は五センチほど高い。
薔薇色の口紅から吐かれる毒は、次々とあたいを攻撃した。
「白鹿さんならまだしも、貴女が彼に釣り合うと思って?底なしに成績も悪い。下品で女らしさの欠片もないじゃない。そのくせどんな顔して彼を惑わせたの?後学のために教えてくださらないかしら。」
「私はね、今度両親に菊正宗君を紹介する予定だったの。お付き合いも結婚も、釣り合う者同士が一番上手くいくってご存知?」
「よくもまあ図々しく、彼の隣に立てるわね。見てなさい。貴女みたいなじゃじゃ馬、きっとすぐに飽きられるわ。」
びっくりするほどスラスラと飛び出す悪口。
よほど悔しかったのだろう。
目には涙すら滲んでいて、ちょっと哀れにも感じる。
当然ながら、黙っていられるほどお人好しでなく、反撃するために息を整えようと深く深呼吸した。
そこへ────
「貴女なんて、剣菱の看板がなければ、見向きもされないわよ!!」
聞きたくない一言が胸を突き刺す。
おい、それは禁句だ。
過去の嫌な記憶が瞬く間によみがえり、清四郎に放たれた台詞が頭の中を回転し始める。
────どこをどうみたら悠理が女に見えるんです!自慢じゃないが、悠理が女に見えたことなんかいちどもありません!
あの時は本当にホッとした。
清四郎にその気がなかったことに。
政略結婚に乗り気なダチなんて、さすがに笑えないから。
でもヤツの言葉は、確実にコンプレックスを抉り、もうそうなると意地を張る事しか出来なかった。
意地は鎧だ。
見せたくない本音を必死で隠す。
本当は…………本当は少しくらい好きだったかもしれない。
恋じゃなくても、あいつが欲しかったのかもしれない。
あの時の台詞が全てを打ち砕いてしまったけれど。
女に見えないと言い切ったくせに、涼しい顔で結婚しようとした男は人が変わったように働き出した。
婚約者を檻に閉じこめ、無理矢理改造しようとする。
悔しかった。
どうせあたいは猿かペット。
人間扱いなんて───されるわきゃないと思ってた。
時々優しいくせに、
その手はおっきくて、あったかいくせに、
女としては見てもらえない。
小さな意地は膨らみ続け、それからは恋愛なんてものから遠ざかろうとした。
けれどこうやって他の女がチラついただけで、驚くほど厄介な嫉妬に支配されてしまう。
素直に好きだと言えない。
側に居てと言えない。
そんな自分がうっとうしくて仕方なかった。
・
・
「あ、あたいは……………」
果たして、剣菱の娘でなくても………清四郎は満足するんだろうか?
もし剣菱がこの世からなくなっても………側に居て、守ってくれるんだろうか?
押し寄せる不安はさざ波を打つ。
女の顔が歪んで見え、いや本当に歪んでいたのかもしれないが、言葉が出てこない。
もし
もし
清四郎にとってその程度の存在なら───
昨日までの幸せが闇色へと変わる。
────ああ。この女、やっぱ嫌いだ。
歯ぎしりしたい気持ちで睨みつけるも、女はふんぞり返ったまま後に引かない。
こうなるともう、優しい言葉なんてちっとも出てきやしないんだ。
「あいつが好きなのは………あたいだ。“剣菱”じゃない。」
「そんな自信、本当にあるのかしら?」
何もかも見透かしたかのような指摘は不愉快だった。
「自信は……………」
あると断言したい。
清四郎が望むような女じゃなくても、選ばれたからには何かが好ましいんだろう。
それが何か、今伝えることは出来ないけれど、それでも胸を張って、清四郎の“恋人”として、この女と対峙したかった。
「あんたの気持ちは解るけど………あたいを攻撃したところで何も変わんないぞ?」
「あら、何故?貴女が身を引けばいいだけの話じゃない?」
耳を疑うような提案。
「身を引く?おまえ、馬鹿にしてんのか?なんであたいが身を引かなきゃなんないんだ!!」
激昂する頭が、片っ端から冷静さを奪ってゆく。
「さっきから言いたい放題言いやがって!だいたい『ひとのもの』って何だよ!いつ、清四郎がおまえのものになったんだ!!」
「そ、それは…………」
「そりゃあ、あたいは成金の娘さ。馬鹿で色気もなくて、トラブルばっか引き起こすよ!でも、でも、清四郎はそれでもあたいのこと………愛してるって言ってくれたんだ!!これ以上余計な口きいたら、本気でぶっ飛ばすぞ!!」
涙目になるほどの怒りをぶつけると、女はようやく少しだけたじろいだ。
胸のつかえがすっきり落ちる。
まだ言いたい事の半分も言えてないけど、やっぱこうでなきゃ、“剣菱悠理”じゃないよな。
「そろそろお開きにしたらどうです?廊下にまで轟いてますよ。」
鼻息を荒くしているところへ、女子トイレの壁がノックされ、外から清四郎の声が聞こえてきた。
「え?清四郎?」
「菊正宗くん?」
想定外の声に慌てて飛び出すと、そこには清四郎をはじめ仲間たち全員が腕組み姿で立っていた。
五人揃えば、目立つことこの上ない。
一定の距離をあけての人だかりはむしろ当然と言えよう。
どうやら薄い壁一枚隔てた会話は筒抜けだったらしい。
通路いっぱいに学生が広がり、ざわついていた。
「な、なんだよ。おまえら、なにしてんだ?」
「何って・・・・・あんたの啖呵を聞いてたのよ。」
「彼女の難癖からずっとね。いやぁ、ほんとひどい言いがかりだったよ。うん。」
美童が頷くと、青くなった東映静香は小刻みに震えながら、清四郎を見上げた。
「わ、私………そんなつもりじゃ………」
さっきまでの勢いはどうした?
肩は震えて、唇は青い。
まるで小鼠みたいじゃないか。
「東映さん。」
「…………は、はい。」
「僕の何が誤解させてしまったのかはわかりませんが、僕は貴女に対して一つの約束も交わしていない。そうですね?」
「……………。」
「勝手な妄想で周りをうろつかれては正直困ります。それに………」
声の温度がぐっと下がる。
本気で不快に思っている合図だ。
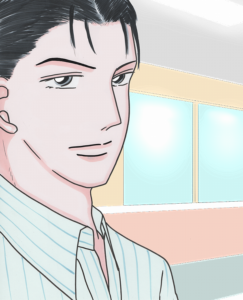
「悠理への暴言は恋人として許し難い。今、ここできちんと謝罪を。」
「ど、どうして私が!?」
「謝罪を!」
それは相手に有無を言わさぬ態度だった。
清四郎の怒りが空気を震わせる。
完全に威圧され、泣き出した女の涙は見ているこっちが辛くなり、思わず目を背けてしまった。
鼻を啜りながら小さな声で「ごめんなさい。剣菱さん。」と言った彼女は、まるでチーターのような速さでその場から立ち去った。
残ったのは爽快感ではなく、もやもやとしたどこか割り切れない感情。
それを頭に置かれた手が、優しく取り払ってゆく。
「さぁ、行きましょうか。」
皆に囲まれながら清四郎の横に立つ自分は、どれだけ恵まれた存在なのだろう。
どれだけ甘やかされた存在なのだろう。
「清四郎。」
「ん?」
「…………あたいは、本当に’あたい’でいいのか?」
「そうですねぇ。自分を守るためにもう少し教養を身につけてほしいところですが、ま、それはおいおい僕に任せて。今はただ此処に居てくれさえすれば…………わりと幸せです。」
そう言って肩に回された腕は力強かった。
可憐と野梨子が優しく微笑んでいる。
魅録が口笛を吹き、美童が茶化す。
どんな悪意も鉄壁の彼らが吹き飛ばし、あたいをこの世でいっちばん幸せな女にしてくれる。
「あたいも…………最高に幸せだよ。清四郎。」
外に出ると真夏の太陽が燦々と降り注いでいて、一等好きな季節をかみしめることが出来る。
小さな不安も、くだらないコンプレックスも、全部陽の光に溶けてなくなってしまえばいい!
この腕があるから────
この五人が居るから────
あたいはあたいらしく生きていけるんだ。
そう確信して見上げた夏空は、胸の空くようなコバルトブルーだった。
