続編
「ごちそうさま!」
「なかなかどうして…………旨かったな。」
「さすがに苦しいですわ。」
「アイスコーヒー飲みたくなっちゃったよ。」
四人が満足そうに腹をさする横で、悠理はひたすら野菜の欠片をかき集めていた。(笑)
無論、活きのいい海老や貝など、残っているはずもない。
今、網の上に横たわるは、キャベツとピーマンの切れ端くらいだ。
とてもしなびた状態で。
「ひどいじょ………」
恨み節をこぼしながら可憐たちを睨みつけるも、それぞれがそっぽを向く始末。
『おまえたちがいちゃついているから悪いんだ』、とばかりに無言の圧力をかける。
唯一、飲み物だけは用意されていて、二人はビール片手に焦げ付き始めた野菜を摘まんでいた。
すると────
(あ……………やべ。)
冷えた三杯目のビールは、引き締めていたはずの下半身を遂に緩め始めたらしい。
トロッと漏れ出す男の名残りは水着の中で不快な感触を与えた。
悠理は焦る。
「せ、せぇしろ………」
「なんです?僕の方も野菜すら残ってませんよ。」
彼もまたあまりの仕打ちに不機嫌さを隠さないが、今はそれどころではない。
「ち・が・う!」
小声で訴えかける悠理はつま先で彼の脛を軽く蹴り、苛立ちをぶつけた。
ようやく異変を感じとった清四郎。
「どうしました?」と身を近付ける。
「あのさ………ほら、アレ………出てきちゃった。」
もちろん何を意味しているか察するも、彼は冷静さを欠かない。
「………水着だから大丈夫でしょう?」(鬼)と沈着に答えた。
「あほっ!気持ち悪いんだよ!」
「…………ふむ。」
───何が“ふむ”だよ!他人事だと思って!
憤る悠理の隣で、清四郎は何かを考えるように腕組みした挙げ句、横目でほかの四人の動向を見つめる。
どうやら次はマンゴーの乗ったかき氷を食べるつもりらしい。
可憐が楽しげにはしゃいでいた。
「仕方ありませんね………」
清四郎はおもむろに立ち上がると、悠理の体を引き寄せ、抱え上げた。
もちろん仲間たちは「何事だ?」と話を中断し、見上げる。
「あなた方の仕打ちに、悠理がふてくされてしまいましたよ。海で遊んでくるとします。」
「あら、かき氷食べないの?」
「後ほど。」
もちろん悠理とてかき氷は食べたい。
だがこのぐっちょりと濡れた不快感からは、いち早く解放されたいのだ。
「べーーっだ!」
なけなしの意地で可憐たちに舌を出すも、清四郎に抱えられた状態では迫力に欠ける。
「…………なんなの?いったい。」
「さあ?」
その不自然な状態から答えは見いだせず、女性二人は首を捻った。
かろうじて美童だけは、ニヤニヤと意味深に笑っていたが。
・
・
・
柔らかな砂浜をゆったりとした足取りで歩く清四郎。
唇を尖らせる悠理は「おまえの所為なんだぞ!」と詰るが、今は彼の腕から逃げることも出来ない。
立てばお気に入りのショートパンツにまで体液が染みついてしまいそうで、恐ろしくて体勢を変えられないのだ。
そうこうしている内に美しく穏やかな海へと到着し、清四郎は彼女を抱えたまま、ショートパンツを器用に脱がし始めた。
それを砂の上に放り出し、ようやく悠理もホッとする。
清四郎もまた自ら白いズボンを脱ぎ去ると、お馴染みの黒い水着姿となった。
「んなとこ来なくても、海の家のシャワーでよかったじゃん。」
「ふ……さすがに、あそこで盛るつもりはありませんよ。狭くて汚いですからね。」
「は???」
目を丸くし、素っ頓狂な声をあげる。
────ま、まさか───
しかし彼の企みに気付いたとて、もう遅かった。
悠理を抱き直し、そのまま海へと入ってゆく清四郎は、腰の辺りまで浸かるほどの水深に到達したとき、悪魔のようににやりと笑う。
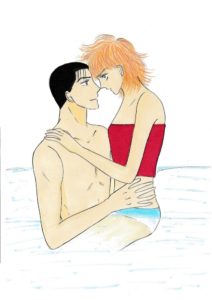
「おまえぇ~。何考えてんだ!」
「解っているくせに。」
啄むようなキスを繰り返しながら、悠理の背中をさわさわと行き来する。
快感を探るいつもの仕草。
どうやら彼は本気の本気らしい。
「おまえの戸惑う姿に欲情しました………まったく………可愛い過ぎですよ………」
蕩けるような声で告げられたとて、此処は海のど真ん中。
いくらなんでも恥ずかしすぎる。
「や、やめよ?な?人に見られ………」
彼の欲情を鎮めようと猫撫で声まで使う悠理だったが、次の瞬間、その声も濡れたものに変わってしまう。
「あっ………ん!」
長い指が水着の中へと侵入。
泥濘を弄ぶように熟れた襞をなぞり始めた。
「たしかに………零れてますね。やらしいな………」
「せ、せぇしろ………んっ!やめ………」
前後に擦り上げながら、小さな芽に己の残骸をクチュクチュとまぶしつける────その行為こそがよほどやらしいじゃないか。
「せっかく奥で出してやったのに………もったいない。」
「はぁ………バカなこと言うなよ………あん………そこ、ダメぇ………」
冷えた水の中で、その部分だけは熱く火照ってゆく不思議。
浮力を借りているからか、清四郎は楽々と悠理の体を支え、嬲り続ける。
「気持ちよさそうな声を出しますね………あぁ、興奮してきましたよ。」
太股に触れる確かな欲情。
硬くそそり立つ肉茎はあまりにも力強く、悠理を圧倒した。
「ここなら、いくら出しても大丈夫でしょ?」
「や、やだ………」
恐れながら首を振るも、清四郎は着実に悠理の下半身を露わにしてゆく。
暴れる足から水着を取り去り、その汚れた部分をわざとらしく見つめる奇行。
悠理は恥ずかしさのあまり、きつく叫んだ。
「清四郎!」
「やはり、出し過ぎましたかね。」
「ば、ばか!!」
ポカポカと頭を叩く手はそのままに、清四郎は悠理の腰を引き寄せ、自分のモノを擦り付けた。そして潮水に流れていく精液とは別の新たな発見を嬉しそうに告げる。
「おや…………コレは僕のモノじゃないな。」
ヌルヌルとした粘液が二人の間を滑り始め、悠理の顔は日焼けよりも赤く染まった。
「だって………」
“んなことされたら──”という言葉を遮り、清四郎は腰を進めた。
「…………挿れますよ?」
「んっ…………ぐ………!」
駅弁スタイルで一気に貫かれ、くぐもった声が喉に絡む。みっちりしっかり入ったはずなのに、清四郎は更なる奥を求め、腰を強く抱き寄せた。
「は………ぁ………いい気分だ。」
「変態ぃ!」
「せっかくの大自然。楽しまないと、ね?」
誰かに見られれば、その不自然な体勢で何をしているかなど一目瞭然。
おそらくは純情な野梨子ですらわかってしまうだろう。
ゆらゆらと、波に合わせるかのように前後左右に揺さぶられ、悠理の胎内はその熱い雄芯をダイレクトに味わう。
力強く脈打つ感触までもが伝わってきて、清四郎がどれほど興奮しているかが解るのだ。
悠理はもはや諦めるしかない。
彼の言うとおり、この大きな海で二人戯れる贅沢はとても良い気分にさせてくれる。
地球に包み込まれているような錯覚。
太陽に祝福されているような喜悦。
「今度こそ………中に出すなよ?」
「善処しましょう。」
そんな言葉は信じなかったけれど───
・
・
その後。
「あの子たち、どこ行ったの?」
「……ホテルに戻ったんじゃないかなぁ?」
「ええ?かき氷食べないつもりかしら。すっごく美味しかったのに………」
可憐の言葉通り、東京ではなかなか味わえない甘い果実がたっぷり乗せられたそれは、まさしく絶品であった。
「まあ、夜には皆で合流できるでしょ。それまでは放置しておいてあげようよ。」
「美童………おまえどうしたんだ?にやけすぎだぞ?」
「本当。気持ち悪い顔ですわね。」
「き、気持ち悪い!?この僕向かってそんなこと言えるのは野梨子、君くらいだよ!」
誰よりも経験豊富な美童だけは、二人が濃密な関係を築いていることを知っていた。
パイナップルの木陰でも、海の中でも───
イケナイ遊びに耽る恋人たちを羨ましく思いながら、それを見過ごしてきたのだ。
────あーあ、僕もナンパしちゃおうかな?
とはいえ、彼らの動向も気になるところ。
何せ、清四郎の血気盛んなまでの欲情は見ていて楽しすぎる。
それに大人しく応える悠理もまた、愚かで可愛いらしい乙女だ。体こそ違えど。
────ま。あの二人だからね。ハマっちゃうとなかなか抜けられないよねぇ。
空は高く、海は底抜けに青い。
一組の馬鹿っプルが少しくらい暴走しても、きっと見逃してもらえるほど、この島の時は悠然と流れているのだ。
欲望の夏は、始まったばかり。
最高の思い出を作るベストシーズン。
