「あ……それ、やっ………!」
悠理が涙目で懇願しても、清四郎はくるりと返した下半身を押さえこみ、ズンズンと奥を穿つ。
本能のまま繋がる獣の様な体勢で、恥ずかしい部分を晒し、掘り起こされる快楽に身を委ねる自分が未だに信じられない。
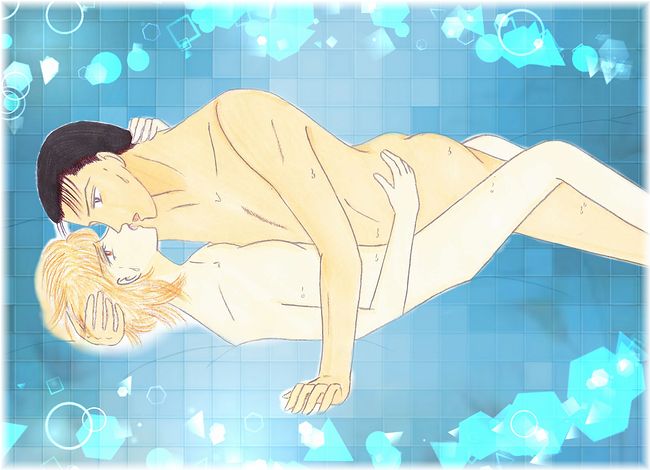
「み、見るなよぉ………」
「今さら………何をそんなに恥ずかしがるんでしょうねぇ。」
くすりと笑う清四郎は、明らかに彼女の恥ずかしがる理由を知っているのだが、そこで容赦するような男ではない。
「可愛いですよ。ここも………そして、ここも。」
さらりと触れた禁断の園。
それと同時に伸ばした手を前から差し入れ、小さく尖った花芽に触れることも忘れない。
「やだぁ!」
相変わらず大きく首を振って拒否を示すが、本当に嫌がっているわけでないことは一目瞭然。
コリコリとした突起が柔らかく揉み込まれ、何も考えられないほどの切ない快楽が悠理を襲ってくる。
「………すごく締まってる。そんなにも中に欲しいんですか?」
━━━違う!
と言いたいはずなのに、口から溢れ出す喘ぎは、まるでそれを受け入れたかのように甘い。
「い……やぁ………妊娠しちゃう。」
「そろそろ頃合いでしょう?」
「ほ…………本気??」
「ええ。」
極限まで膨張した欲棒。
そんな凶器で胎内を撫で回すよう擦り付ける清四郎は、慌てて後ろを振り返った妻へと優しく微笑みかけた。
・
・
・
二人は結婚二年目の若夫婦。
現在、都内にある剣菱家所有の高級マンションで二人暮らしをしている。
若くして結婚に踏み切った彼らだが、交際期間を含めてもまだ三年足らずだ。
もちろん二人にけじめを求めたのは、母、百合子である。
‘人形の様に可愛い孫’
それを欲する彼女の熱意は、今もまだ消え去ってはいないのだから。
大学も四年目を迎えた頃。
長年友人だった二人に一つの転機が訪れる。
高校時代と比べ、段違いに忙しくなった清四郎と、無節操に遊び呆ける悠理。
特に将来をシビアな目で見据えている男は、十分単位のスケジュールに追われる日常だった。
だが、そんな彼も仲間達との交流は欠かさない。
息を充分に吐き出せる場所はそこしかなかったのだから。
その週末も、6人はいつものようにナイトクラブで弾けていた。
馴染みの店だった為、顔見知りは多く、中でも美童のファンは圧倒的な数を誇っていた。
高校時代よりもあからさまな誘い。
客の半数が女、という状況下で、彼女たちが清四郎や魅録にまで目を付けるのは必然だ。
美童はもちろんのこと、二人の男振りも相当なものである。
特に上質なスーツに身を包んだ清四郎は、ハゲ鷹の群れに落とされた金の卵のようなものだった。
・
・
・
「おまえって、結構モテるんだな。」
爽やかなモヒートを片手に、悠理は清四郎の隣に座る。
グラスの水滴がカウンターに帯を引き、未だあどけない爪がそれをなぞった。
柱の陰に隠れた喧騒届かぬそこは、不健康な空気を断ち切り、酔いを落ち着かせるにはもってこいの空間である。
「おまえほどじゃありませんよ。さっきも変わったオカマに声をかけられていましたね。」
「オカマも女もお呼びじゃないやい。」
「僕もです。」
ほろ酔い加減の悠理と、顔には表れないがほどほどに酔いが進んでいる清四郎。
軽口を叩きながら、プッと吹き出す。
「おまえとこうして居る方が落ち着くんだ………。」
「ふん。……んなこと言ってるから‘ゲイ’だの‘バイ’だの、噂が飛び交うんじゃん?」
「今さらもうどうでもいいですよ。ガツガツした女性にはこりごりですし。」
それは過去の経験をさらりと匂わせる発言だったが、悠理は敢えて聞き流した。
「このまんまじゃ…………いつまで経っても結婚できないぞ?おまえ、年頃になったら‘したい’って言ってただろ?」
「ええ。だから、その時はよろしくお願いしますね。元婚約者殿。」
「━━━━━え?」
何気なく告げられた言葉は悠理の顔色を変える。
聞き間違いかと思い目を瞠ると、彼は片目を瞑り、くすりと悪戯めいた笑いを見せた。
「………冗談です。そんな顔しないで下さいよ。傷付くじゃないですか。」
「んなの、面白くもなんともないぞ!」
そう詰って頬を膨らませた悠理だったが━━・・
「……そう、ですね。おまえは僕を嫌っているわけだし……確かにこんな冗談は迷惑なだけ、か。」
さっきまで柔らかな微笑みすら浮かべていたはずの清四郎が、一転真顔になる。
悠理はそんな彼の切り返しに、胸がズキンと痛んだ。
「別に嫌いじゃないぞ!その辺、誤解すんなよな!」
「………かといって好きでもないでしょう?」
好き━━━なんて特別な意味を持つ言葉は、この六人の中で存在しなかった。
少なくとも今までは………。
もやもやとした胸を抱え、悠理は考える。
好きか嫌いか━━━そんな二択を提示されたら‘好き’と答えるしかない。
だが今、何故かその言葉はするりと口から出てこなかった。
これが魅録なら‘愛しちゃってるよ’と言えただろうに。
これが美童なら‘はいはい。スキスキ’と軽く流せただろうに。
なのに、今の清四郎にはどうしても言えないのだ。
何故?
いったい他の二人と何が違うのか………
混乱する悠理を清四郎が笑う。
「そこまで悩まれると本気で凹みますな。」
酒のせいか、傷ついた顔は少し赤らんで見える。
黒い瞳が哀しさに揺らいだ。
『………らしくない!ちっとも清四郎らしくないぞ!』
いつも尊大すぎるほどエラそうな男だった。
呑気に騒ぐ仲間達をどこか遠巻きに眺めていることも多かった。
その冷徹な目で。
自分の事など女扱いどころか、散々猿か犬みたいに転がしてきたじゃないか。
しかし感情よりも先に、悠理の身体は動いていた。
薄く染まった頬へと手を伸ばし、優しく包み込む。
「…………好きだよ?」
「…………え?」

彼が目を瞠った瞬間には唇を合わせていた。
慰めの意味を込めた、たった数秒間の淡いキス。
そっと離れた時には、互いに火を吹かんばかりの真っ赤な顔で━━━
それがもう、特別な意味を持っていることは明らかだった。
清四郎が酒の勢いで告げた言葉は、彼の隠された本心だ。
本能的にそれを読み取った悠理は、急速に心が逸り、彼に対する温かな感情が芽生えてくる。
けれどそれを酔いのせいにだけは、したくなかった。
次の日、彼の腕の中で目覚めた彼女が何よりも気になったのはその表情。
しかし、優しい笑顔で‘おはよう’と挨拶された時、自分達はもうただの友人ではないと気付く。
越えてしまった一線。
夕べは執拗なほど‘好きだ’と言い、抱き合った二人。
いつの間に、このような激しい想いを育てていたのだろう。
悠理は冷静な頭で清四郎を見つめ、そして自然と顔を近付けた。
「清四郎。」
「どうしました?」
「あたい………もう、おまえのこと………」
「特別に思う?」
代弁された言葉に頷くと、清四郎はギュッと抱きしめ、至る所に口付けてきた。
「僕もおまえがこの世で一番特別です。」
・
・
・
それからはトントン拍子に交際が進み、親の思惑だけでなく、二人きりの生活を求め始めた彼ら。
お互いの恥ずかしい部分も醜い部分も全てを曝け出し、小さな喧嘩をしながらも仲睦まじく暮らしていた。
子供の件に関しては清四郎に任せきりだった悠理。
だからこそ現実味がなかったのだろう。
夫の提案に驚いてしまう。
「もう少し二人きりで居たかったですか?」
「そ、そういうわけじゃ………」
言葉を濁すが図星である。
「実はね。来春から三年ほど海外赴任が決まりそうなんです。おまえは寂しがり屋だから、子供でも居たら楽しめるかと思ってね。きっとお義母さんたちも喜んでサポートしてくれるでしょうし……」
「え?」
急速に冷える体温。
耳を疑うような言葉には、更に現実味が無かった。
━━━子供とあたいだけ残して海外暮らし??何考えてんだ、こいつ!
情緒や人間味に欠ける男だとは知っていた。
だけどこれはさすがに許せない発言である。
悠理は清四郎から強引に離れると、鋭い視線で夫を睨み付ける。
その熾烈な光に彼は思わずたじろいだ。
「悠理?」
「あたい、やだ。」
「そうは言ってもこれは仕事ですから………。」
「連れてけ!」
「……英語もろくに喋れないくせに本気で言ってるんですか?遊びじゃない。生活をするんですよ。」
正論に言葉を詰まらせる悠理だったが、ここは譲れない。
一人きりでこんなマンションに残されたら、それこそ退屈で気が狂ってしまう。
たとえ子供が居ても、清四郎が居なければ意味がない。
『そんな当たり前の事、なんで解んないんだよ!この朴念仁!』
「言葉なんて何とかなるさ!だいたい子供だって向こうで作ればいいだろ?それよりもおまえ、あたいの居ない生活に耐えられるのかよ!」
「そ、それは……その、もちろん寂しいですが………三年の事ですし……」
もごもごと言葉に詰まる夫を、悠理は更に追い立てる。
「寂しい?寂しいなんてもんじゃないぞ!あたいは三年間も絶対に我慢に出来ない!欲求不満で頭がおかしくならあ!清四郎はあたいが他の男と遊んでても良いのか?こんなとこに一人で置いてってみろ!色んな男、取っ替え引っ替えしてやる!良いんだな?」
清四郎は限界まで目を見開いた。
妻のこんな台詞は想定外。
いくら怒りに囚われているとはいえ、度しがたい内容だ。
━━━彼女が他の男と戯れている。
その場面を軽く想像しただけで、胃が沸騰するかのような怒りがこみ上げる。
「良いわけあるか!おまえは僕だけのものだ!」
腕を掴まれ、痛みを感じるほど強く押し倒された悠理は「ふん」と鼻を鳴らす。
「ならちゃんと側に居ろよ。おまえがあたいをこんな風にしたんだか………んっ!」
言葉ごと奪う、噛みつくようなキスは、喉の奥までをも容赦なく蹂躙した。
凶暴すぎるキスは嫉妬のせい。
そう理解した悠理は身体の強張りを解き、夫に身を任せる。
唾液を啜り、たっぷりと絡み合う舌が、互いを求めて暴走し始める。
悠理とてさっきまで受け入れていた昂ぶりが欲しくて堪らないのだ。
混じり合う熱が急上昇し始め、彼女は思わず足を擦り合わせた。
明らかにそこは濡れている。
どろりとした欲情が帯を引くように…。
「早く入れて……せぇしろ!も、我慢出来ないよぉ。」
切羽詰まった様子で甘える妻を見て、夫はようやく苦笑する。
「ではコンドームを………」
「いい!あたい今日は良いから……そのままで……」
「本当に?海外で子育てする覚悟はあるんですね?」
「頑張る……だから、中で出していいよ?」
愛する女からの魅力的な誘いに清四郎は最後まで迷ったが、結局は抗えなかった。
・
・
・
中断されていた所為なのか。
それとも焼け付くような嫉妬の名残?
清四郎の勢いは激しく、悠理はガクガクと揺さぶられる身体を必死でシーツに繋ぎ止めた。
もう何度吐き出されたかも解らない夥しい量の精液が、健気に受け止め続ける秘部から漏れ出し、そこから淫らな音を響かせる。
「せ、せぇしろ……も、休ませて…………汗、ぬるぬるして気持ち悪いよ。」
止め処なく溢れ出す汗。
それと共に、震えが止まらないほどの快感が彼女の身体を完全に支配していた。
息を上げながらも、夫をうっとりと見上げる。
官能に囚われた甘い仕草。
清四郎は嬉しそうに笑い、その我が侭を聞いてやることにした。
「そうですね……では……風呂場に行きましょう。」
繋がったままの妻を軽々と抱きかかえた夫は、真っ直ぐにバスルームを目指す。
寝室から扉一つで繋がっているそこは、美肌の湯として有名な温泉が24時間いつでも浴槽に注がれる仕組みとなっていた。
淡く濁る浴槽にそのまま浸かった彼は早速逞しい腰を繰り出し、悠理を喘がせ始める。
「あ……やぁ…………あ、やっ…も、休ませるって……」
「少しだけ休ませてあげたでしょう?」
それはここへと移動してくる僅かな間の事。
悠理はがっくりと項垂れ、夫の肩にせめてもの抵抗とばかり、カプリと噛みついた。
「いくらでも噛みつけば良い。たとえおまえが泣いて懇願しても、僕は決して離れませんよ。」
「……え?」
「これはお仕置きなんです。夫に対して、あのような暴言は許されるものではありませんからね。」
清四郎は奥深くまで突き上げると、汗でしっとりと濡れた耳元に低く囁く。
「いいか?さっきみたいな台詞は二度と言うな。おまえの身体はたとえ髪の毛一本たりとも僕の物だ。ここも、ここも、この先にある子宮も全部、僕だけの物だ。浮気など死んでもさせない。」
それは初めて耳にする、鉛色の声だった。
常に冷静さ見失わない清四郎が、今は怖いほどの怒りで悠理を脅している。
そう、彼はずっと怒っていたのだ。
いつもの表情で妻を可愛がりながらも、身の内は独占欲という名のマグマで燃え盛っている。
悠理は自分の失言を初めて悔いた。
身体は快楽に溺れきっているというのに心はひんやりと冷えていく。
「ご、ごめんなさい…………」
言い訳など許される状況ではない。
恐怖に涙が零れ、露となって清四郎を濡らす。
「悠理、僕を怒らせるなよ。おまえの我が侭ならどれだけでも聞いてやるが、この身体を他の男に触れさせることだけは絶対に許さない。一生だ。」
コクコクと頷く悠理は小兎のように目を赤くしている。
清四郎は「さすがに言い過ぎたか」と反省しながらも言葉では慰めず、瞼へのキスで代わりとした。
「ふ……ふっ…………ううっ……」
夫の厚い胸板にぴったりと寄り添い、彼女はしくしくと泣き続ける。
それはもう恐怖のせいではなく、惰性で流れる涙であったが……
清四郎は「参ったな」と小さく呟くと、悠理をさっきと同じように抱きかかえたまま、洗い場に身を移した。
そして軽く首を振った後、彼女の中から名残惜しさを感じさせるようにゆっくりと離れる。
白濁したものがドロリと流れ落ち、その美しい脚を容赦なく汚した。
そこへ何度かかけ湯をした清四郎は、タイルの上に跪く。
悠理は何をするのだろうと赤い目で瞠ったが、彼が秘所の肉を押し広げ、小さな快感の芽を舌先でつつきだしたのを見て、一気に頭がスパークした。
「あ……そんなの、今……ダメだってばぁ……!」
「少々苛めすぎましたからね。可愛がってやりますよ。ほら、たっぷりと感じなさい。」
清四郎の舌遣いは絶妙だ。
悠理はそれだけで過去何度も気絶させられた事を思い出していた。
濡れた花弁へと下りてゆく舌。
嬲るように何度も下から舐め上げ、そのまま花芽へと吸い付き、小刻みに左右へ揺らされる。
「ひぁ…………ぁ、いっ…………あぁああーっ!!!」
押し殺すことなど不可能な喘ぎが、バスルームに響き渡る。
清四郎は決して止めない。
どれだけ懇願しても、彼の舌は動きを止めようとはしない。
今すぐにでも弾けそうな快感に頭を激しく振る悠理は、夫の髪をくしゃくしゃにかき混ぜ、思いを伝えようとする。
「や、や、やだぁ………………おかしくなるよぉ!!」
その喘ぎが合図となったのだろう。
清四郎の歯は可愛く膨らんだ粒を軽く扱き、一気に高みへと押し上げる。
「ひぃぃ!!!」
次々と襲い来る快感。
身悶え、痙攣した悠理はとうとう脱力し、咽喉を反らしたまま意識を失うよう崩れ落ちた。
もちろんその身体は夫の腕がしっかりと抱き留める。
溢れんばかりの愛しさを双眸に浮かべ、労るように肌を撫でながら、半開きになった唇をそっと吸い上げる。
「あんな台詞を聞けば、おまえから片時も離れられないと解りましたよ。これからは全力で束縛させて貰いますからね。覚悟するように…………」
・
・
・
その後、悠理の口から’浮気’を示唆する言葉は発せられていない。
あれは一生に一度の失言で、心にもない台詞だったと誓って言える。
清四郎の激しい独占欲に驚いた悠理だったが、今は喜びと共にそれを受け入れていた。
まだ膨らみを見せないお腹を優しく撫でながら、引っ越し業者にテキパキと指示を出す夫を見つめる。
「父ちゃんも暫くはあっちの別荘に住むってさ。」
「ああ、やはりそうなりましたか。」
可愛い孫への執着から、百合子は悠理たちと住むための大きな別荘を購入した。
この先、万作から確実にシフトしていく愛情は、留まることをしらないだろう。
「あーあ、ひらひらレースの部屋ばっかは、やだじょ。」
「それはまあ、…………甘んじて受け入れることにしましょうか。」
夫はこう見えてウキウキしている。
百合子に負けじとベビー用品を買い漁り、育児書を舐めるように熟読していることも知っている。
━━━意外と子供好きなんだな、こいつってば。
悠理はクスッと笑みを溢すと、そろそろ到着するであろう仲間達を出迎えるため、ソファから立ち上がった。
