────目を合わせて欲しい。
そう言えば、悠理は照れたように顔を背けた。
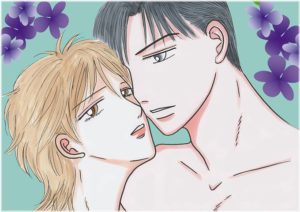
こんな関係になって早半年。
“恥ずかしい”だなんて…………
そんな柄でもないくせに、いつもいつも彼女は目を逸らす。おまえの顔を見つめながらイきたいのに──
最後の最後に手で覆うなんて止めてくれ。
懇願するよう告げれば、悠理は真っ赤な顔で首を振った。
「あたい…………変な顔してるもん。絶対、不細工だもん。」
どんな顔をしていても、僕にとっては大事なその瞬間。
見逃し続けてきたこと自体、腹立たしい。
「今更、おまえのえげつない顔で萎えるような僕じゃありませんよ。」
「…………そ、そんなえげつない顔、見せてきた?」
「過去を振り返ってみなさい。相当ですから。」
泣きそうに歪んだ顔を引き寄せ、口付けを。
「愛してるから。………どんなおまえでも絶対に愛せるから……………」
そっと頬を重ね合わせれば、悠理はようやく僕の目を見つめた。
「も…………クセになっちゃってるし………今度するときは、手、押さえてて?」
「それは…………ずいぶんと魅力的な提案ですな。」
興奮が立ち上る。
拘束を嫌う悠理を押さえつけることが、僕にとってどれほど甘美な誘惑か、彼女は解っていない。
一瞬にして昇りきった欲望を隠さぬまま舌なめずりしてみれば、悠理は諦めたように瞳を閉じた。
その瞼に啄むような甘いキスを。
そして再び始まる…………官能の夜。
