最初、その子を“少年”だと思った。
“一夜の夢”を売る“イケナイ青少年”だと───
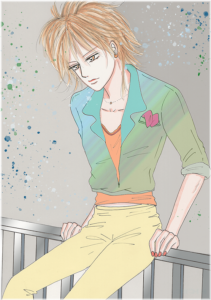
この界隈ではそういった類の商売が多く、もちろん需要と供給は成り立っているわけで、刑事の俺がいうのも何だが、それも“必要悪”みたいなもんだと認識している。
それに全てがヤクザ絡みというわけでもない。
ただふらり、小遣い稼ぎを目的としてくる奴もいるし、人肌を求めるが故、この路地に寂しそうな顔で立つ者もいる。
新宿はとにかく猥雑な街だ。
いちいち気にしていても仕方ない。
気にするだけ損というもの。
なのに、俺は目が離せなかった。
彼、いや彼女から。
大人びた顔立ちにほんの少しの憂鬱を纏わせ、ただジッと地面を見つめている。
煩いほどのネオンが溢れかえる街の片隅で、何かを耐えるかのように、ひたすら静かに、美しい横顔を強ばらせていた。
職業柄、今まで色んな輩を見てきた。
だが彼女ほど“個性ある美”を感じた人間はいない。
細く長い手足は敏捷さを思わせ、色素を抜いたようなボリュームある髪は、闇夜でも見失うことはないだろう。
年齢は恐らく………14、5。
経験によるその読みは正しく、後々、俺は彼女の驚くべきプロフィールを知ることとなる。
時間を気にする様子もないまま、彼女、“剣菱悠理”はそこに立ち続けていた。
正確にはフェンスにもたれ掛かるように。
俺はその端正な顔立ちと雰囲気に目を奪われ、自分の立場すら忘れそうになっていた。
初夏、といっても蒸し暑さは例年にも増してひどい。
それも車内。
古い車のエアコンは臭くてかなわない為、ここは忍耐を要する。
俺のシャツがじっとり濡れやがる。
丸二日着替えてないから、匂いも鼻につく。
不愉快きわまりない状況。
「富樫さん、腹減りませんか?」
七つ年下の“槇野”は新入りで、俺直属の部下だ。
頭はいいが勘は鈍い。
「どうして刑事になったんだ?」という質問に、「“太陽にほえろ!”が好きだったんすよ。」と軽口で答えた馬鹿野郎である。
捜査四課(暴力団を取り締まる)──なんて野蛮な課に回されて、果たしてこれからやっていけるのかどうか。
「まだだ───でも今ここを離れるわけには………」
香港系マフィアと結託したこの辺りを締める組のチンピラが、最近二件の殺人をやらかしたと聞く。
犯人の目星はついているため、そいつの根城を探っているわけだが、どうやら今夜はまだ帰ってきてないらしい。
まずは手探り。
奴の動向を調べているのだが───
「俺、買ってきましょうか?マ●クとバ●ガーキ●グ、どっちが好きです?」
「………………俺は珈琲だけでいい。」
「了解っす!」
まあ、居ても居なくても大して変わりない存在だ。
どうせ狭い車の中、一人のほうが息がしやすい。
少しだけ窓を開け、煙草を吹かしていると、ようやくあたりをつけていた『ホシ』のお出ましだ。
黒シャツにジーンズといった、ラフな格好をしている。
髪は短めの茶髪。
耳には金色のピアスが光っていた。
目つきは悪い。
人生に絶望した顔にも見えるが、野心を秘めたような光も失われてはいない。
奴が雑居ビルの隙間にある鉄製の階段を上ろうとして、ふと“彼女”の存在を目に留めた。
距離は数メートル。
目立つ容姿をしているが、少年にも見える彼女に声をかけるとは、なかなかやるな、と感心させられる。
男の声は聞こえないものの、恐らくはナンパ。
一夜の相手を見繕うつもりだ。
しばらく問答があった後、奴は急にその拳を振り上げた。
どうみても自分より遙かに華奢で力ない少女の襟首を掴み、殴りかかろうとしている。
俺は慌てて車のドアを開け、二人の元へ駆けだした。
仕方ない、緊急事態だ。
それにあの美しい顔が腫れ上がるのを見たくはない。
だが俺が駆けつけるほんの数瞬の間に、決着はついてしまった。
地べたにうずくまり嗚咽する男の不甲斐ない姿。
滴る涎がシミをつくってゆく。
「気易く触ってんじゃねぇ!」
怒号が響きわたり、俺はピタリと足を止めた。
鋭い視線は全ての者を蹴散らすかのように輝いている。
恐らくは足蹴り一発で奴をのしてしまったんだろう。
喧嘩慣れした勇ましい立ち姿で男を見下ろし、今にも唾を吐きかけん勢いだった。
「おい…………大丈夫か?」
愚問だと思ったが声をかける。
すると彼女は訝しげにこちらを見上げ、「誰にモノ言ってんだ?」と悪態を吐いた。
「怪我は────なさそうだな。」
唐突に声をかけてきた大人などに興味はないらしい。
踵を返し立ち去ろうとするも、俺はつい手を伸ばし、彼女の肩を掴んだ。
細い。
こんな細い体で、よくもまあ───
「なんだよ、おっさん。あんたも喧嘩売ってんのか?」
おっさん───ね。
まだ30手前なんだけどな。
決して荒んだ印象を与えない少女なのに、口から出る言葉は汚く、そんなギャップにこそ興味を惹かれた俺は、思わず力ずくでこちらを振り向かせてしまった。
「いてっ!!なにすんだ!?」
「あ………すまん。少し話を聞きたくてな。君、この男になんて声をかけられたんだ?」
もちろん『殺人事件』については口を塞ぐ。
「“ちょっと付き合えよ。あんたなら俺の相手にちょうどいい。”───って言われただけだよ。」
「え、それだけ?」
「………ったく、馬鹿にしてんのかよ。この辺であたいに喧嘩で勝てる奴なんかそうそういないってのにさ。」
どうやら彼女は奴の言葉の意味をはき違えたらしい。
まさかナンパされているとは思わず、喧嘩を売ってきた、と勘違いしたのだ。
「ハハハ!」
「────なにが面白いんだ?」
「いや…………君みたいに綺麗な子が、そういう風に捉えるとはね。喧嘩慣れしていても、男慣れはしてないってことか。」
「…………男慣れってなんだよ。」
ヤマアラシのように尖っていた雰囲気がほんのだけ少し緩む。
よくよく目を凝らせば、まったくもって女の子にしか見えない。
あと十年、いや五年もすれば、ひっきりなしに男を呼び寄せるだろう。
「まだ中学生には早かったな。」
「???」
うずくまっていた男がヨロヨロと立ち上がり始めたので、意識をそちらへと戻す。
こういう捕り物も悪くはない。
きっかけなんぞに拘るのは、愚かな刑事のやることだ。
「おい。生きてるか?ちょっと話が聞きたいんだがな───」
「ごほっ………あんた…………誰だよ?」
どうやら口をきけるまでに回復したらしい。
憤りよりも、激しい痛みを耐えるかのように前屈みになっていた。
俺は奴の質問に応えるべく、懐から手帳を見せる。
その瞬間、顔色が赤から青へと変わり、俺との距離を空けようとするも、すかさず手を掴み、間合いを詰めた。
「君、夜分に申し訳ないが、署まで同行願えるかな?」
「なんで………だよ!俺、ナンパしてただけだぞ!あの女の方から暴力を振るってきたんじゃねぇか!」
「もちろん彼女からも事情を聞くから安心しろ。」
「げ!あたいもかよ!」
彼女についてはあくまで、個人的な思惑によるもの。
本来なら必要のない聴取だ。
「おい、なにやってんだ?悠理。」
そこへ───どうみても尖った感じの少年が声をかけてくる。
ピンク色の頭は真っ直ぐな眼差しでこちらを見つめ、直ぐに何かを悟ったように目を細めた。
「魅録!ちょうどいいとこに来たじゃん!」
俊敏に駆け寄り、頬擦りする勢いで懐く。
仲の良い友達といったところか。
「おまえ………また一人で暴れたのかよ?」
「ち、ちがわい!この男から喧嘩売ってきたんだ!」
真実は異なるが、結果として暴力沙汰。
察するに、普段から同じような騒ぎを起こす少女らしい。
「悠理は喧嘩っ早いからな。どーせ必要以上に噛み付いたんだろ?」
ハハハ!と笑い飛ばす彼の表情に何の後ろめたさも何もない。
『魅録』という少年もこれまた年の割に大人びた印象を与えた。
「笑い事かよ!あたいまで警察に引っ張られるとこなんだぞ!魅録、おまえ警視総監の息子じゃんか。何とかしてくれよ!」
「おいおい………なんつー無茶なことを………」
警視総監────?
息子?
…………まじかよ。
「あ、富樫さーん!何してんすか!?」
呑気な声で駆け寄る槇野に気が緩み、ついホシの手を放してしまった。
あり得ない失態。
ここで逃げられでもしたら元の木阿弥だ。
しかし勢いよくトンズラしようとする男の足を、ピンク頭の少年が器用に引っかけ、その後、驚くほどの俊敏さで勇ましい少女が上からのしかかる。
瞬きする間のコンビネーション。
手慣れた様子で関節技を決め、動きを封じた。
「………逃げてんじゃねぇ!」
気合いの入った怒号もこれまたいかつい。
「た、助かったよ。」
唖然とする槇野を促し、男の身柄を確保。
是非とも彼女に署へ来て貰いたかったが、警視総監の息子のお友達を連行できる権力など持ち合わせてはいない。
刑事といえどもしがないサラリーマンなのだから。
それからというもの───
ふと街角で似た少女を見つけると、足が止まるようになった。
いい年して恥ずかしい話だが、どうやら魂を抜かれちまったらしい。
たかだか15の子供に…………。
イカれてるとしか思えない。
簡単に調べることが出来た彼女の素性。
驚いたさ。
とても“お嬢様”とは思えない言動に。
俺のような底辺刑事には、到底届かない高嶺の花だったということに。
忘れるのが一番だ。
それこそが大人の常套手段。
狡いと言われようが構わない。
いい年した刑事が本気になる相手でもない。
案の定、くそみたいなヤクザどもを追いかけている内に記憶は薄れていった。
