注意:美→可→清×悠 的なお話です。
オレンジ色の間接照明。
目にも目映い夜景が広がる窓。
乱れたシーツは情事の名残り。
まるで映画のワンシーンのようにロマンチックな夜。
だけどあたしはときめかず、諦めにも似た溜め息を吐く。
「どうして、僕を選んだの?」
金髪の青年は、意外なくらい男っぽい仕草で体を起こし、あたしの背中にゆっくりと指を這わせた。
探し出したピアスを装着していたところへの不意打ち。
粟立つ肌を官能から切り離し、彼の馴れ馴れしい手を抓る。
「痛っ!」
「あんたなら後腐れがないと思ったからよ。」
「後腐れ……って、酷い言い草だよね。」
「そう?実際その通りでしょ?」
ピアスの後、ブラジャーに腕を通し始めたあたしを、美童はもう一度シーツの中へと引きずり込んだ。
これもまた意外なくらい力強くて、抵抗する気が削がれる。
「強気なのは可憐らしいけどさ。ちゃんと泣かないと後々辛いんじゃない?今回ばかりは。」
「よ、余計なお世話よ。」
「僕の身体を使ったんだ。このくらいのアドバイスは当然でしょ?」
言葉に詰まっていると、嗜める様なキスが降ってくる。
その瞬間、何故か切ない気持ちになった。
━━━━あぁ……あたしたちはもう、大人なんだ。
彼は五年前と比べ、すっかり落ち着いた青年へと成長したし、あたしもまた男の温もりに縋る事が出来る計算高い女となった。
叶わぬ恋を飲み込んで、友人だった男をベッドに誘う。
数多の恋愛を繰り返してきた美童には、きっと全てがお見通しだろうけど。
「明後日、だね。結婚式。」
「……………そうね。」
「本当は出席したくないんじゃない?」
「そんなことないわ。ちゃんと……祝福してあげなきゃ。」
自分のためにも。
「どうせなら………清四郎に慰めてもらえば良かったのに。」
「止してよ。結婚前の男に手を出すほど外道じゃないわ!それにあいつは………」
絶対にあたしを受け入れない。
悠理に溺れきった男は、彼女を裏切ることなんて出来ないから。
「まあ、ね。でも本当は抱かれたかったんでしょ?」
「………だから、止めてってば。」
「三年、もう四年になる?」
「美童!!」
睨み付けても彼は堪えない。
穏やかなブルーアイは悲しげに細められ、その大きな手はあたしの頬を優しく撫でた。
「あんたこそ…………どうしてあたしの誘いに乗ったのよ。」
「それは……ほら、可憐には恩があるからさ。」
「━━━恩?」
聞き慣れない言葉に神経が尖る。
「君とペンパルになったおかげであいつらと知り合えたわけだし、平凡だったはずの人生がゴロリと変わった。本当はすごく感謝してるんだ。可憐の社交性と優しさ。それに…………」
「それに?」
「僕に本当の恋を教えてくれたこと。」
子供っぽい台詞を吐く美童の唇は、明らかな欲情を帯びながらあたしを誘う。
情熱的なキス。
せっかく鎮まっていたはずの官能に火が灯り始め、結局そのまま彼の愛撫に身を任せた。
・
・
そう、四年にもなるのだ。
あたしがあの冷血漢に恋をしてから。
それは突然だった。
あれほど女扱いしてこなかった悠理に、清四郎は恋をした。
そして悠理もまた、奇跡的にそれを受け入れた。
彼らの間に何があったかは知らない。
だけど、磁石がくっつくような勢いで二人は恋に落ちた。
皆は驚き、狼狽える。
仲間内で誰よりも恋に縁遠い二人だ。
波紋のように広がる疑問。
それでも祝福の言葉を投げ掛け、彼らが上手くいくようにと願った。
もちろんあたしも━━。
その時は清四郎のことなど、何とも思っていなかったはずなのに。
しかし彼は徐々に変化してゆく。
溢れんばかりの愛情と慈しみ。
優しさと包容力。
清四郎は一途な愛を悠理へと注ぎ続けていた。
そして悠理もまた、彼の本気に流されるよう、女性らしさに目覚め始める。
そんな変化は見ているあたしたちを驚かせると同時、恋の威力を思い知らせた。
清四郎は理想的な恋人に徹し、悠理もまたそんな彼に甘えた。
羨ましかった━━正直。
・
・
あれは皆で飲みに行った夜。
確か夏休みに入ってすぐのことだったと思う。
その頃のあたしは久々に本気になった相手と破局し、ちょっぴり・・・いやかなり荒れていた。
だけどそんな日常茶飯事に誰も付き合ってはくれない。
お洒落なバーで二次会を始めた頃、10度目の失恋話に耳を傾けてくれる仲間は清四郎くらいしかいなかったのだ。
甘いカクテルを立て続けに飲み、すっかり酔っ払いだったあたしは、カウンターで背を向ける清四郎の隣に腰かけた。
「どう?悠理とはうまくやってる?」
「不躾になんです?上手くいってますよ━━━今のところは。」
肝心の恋人は背後のテーブルで大虎状態。
魅録が呆れながらも相手をしていた。
「キスとかしてるの?してるわよねぇ?もう三ヶ月も経つんだし。もしかしてベッドインしちゃった?」
「随分と酔いが回ってますね。そろそろ水に切り替えた方がいいんじゃないですか?」
バーテンダーに氷水を頼むその横顔に不機嫌な様子は見当たらない。
「ふん。あんたって面白くないわ。そんなんじゃ、悠理にだって振られちゃうんだから!良い男は女に優しくなくっちゃね!」
アルコールとは怖いものだ。
いつもなら言えない悪態も、するすると口から滑り出す。
そんなあたしに清四郎はクッと笑いを噛み殺し、なめらかな動きで顔を近付けると、耳元で囁くよう告げた。
「可憐。僕が欲しいものを我慢するような男に見えますか?」
瞬間、尾てい骨が震えた。
ゾクゾクするほど甘い低音。
思わず『ヒッ!』と声を洩らしたのも仕方なかったと思う。
それはあくまで、清四郎の意地悪。
からかうつもりだっただけだ。
しかし、そっと見上げた先にある瞳は、恐怖すら感じるほど‘男’だった。
意識したのはそれからだ。
だけどあたしは腑に落ちなかった。
これでも色んな恋愛経験を積んできたつもりだったし、清四郎よりも良い男と言葉遊びのような戯れを重ねてきた。
━━━あんなことくらいで心を鷲掴みにされるほど、この可憐様は簡単じゃない!
最初はそう否定しながら手当たり次第、違う男と付き合った。
それで自分の誤りを正せるのなら、安い物だと思った。
けれど━━━
悠理の隣にいる清四郎はどうしても魅力的に映り、女の醜い嫉妬が持ち上がってくる。
口にも出せない。
態度にも出せない。
自由を奪われた恋がこれほど苦しいだなんて、ちっとも知らなかった。
恋に猪突猛進だったあたしを、ここまで苦しませる清四郎が憎くなった。
かといって、悠理から奪うなんて考えたくもない。
彼女は大切な友人。
かけがえのない友人なのだ。
心に鍵をかけ、偽りの恋愛ごっこを重ねる。
美童にバレたのもきっとこの頃からだと思う。
・
・
大学構内で、二人はいつも一緒にいた。
正確には清四郎が悠理から片時も離れなかった。
悠理はそれを鬱陶しそうに追い払うけど、彼は絶対に離れなかった。
その理由は簡単。
彼女の成長ぶりが男を寄せ付けると危惧していたから。
悠理は元々美人で、家は大金持ち。
男にモテなかった理由は色気の無さだけ。
愛されるようになってからは、あたしですら目を瞠るほど美しく輝いて見えた。
目を離す危険性に怯える清四郎もまた、恋の苦しみを知る一人だ。
恋愛においては、卵から孵った雛のような悠理。
誰彼なしに愛想を振り撒かれては元も子もないのだろう。
清四郎の過保護ぶりと束縛は日を追うごとに、ひどくなっていく。
「そんなにも心配?」
「━━━なんの話です?」
二人きりになった時、そう尋ねた。
白々しく惚けようとする食えない男。
「悠理の気持ちが信じられないの?」
「随分と攻撃的ですね。また失恋でもしましたか?」
それはいつもの軽口。
けれどあたしは飽和状態だったのだろう。
張り詰めていた神経が音を立てて切れ、気が付けば清四郎の胸ぐらを掴み、唇を押し当てていた。
「!!」
キスだけなら━━━
キスだけなら━━━
それはどんな理屈であろうとも、してはならないこと。
相手は悠理の恋人。
悠理だけのモノなのだ。
反射神経に長けた男が珍しく硬直している。
しかし舌を入れようとした瞬間、我に返り、あたしを思いきり振り解いた。
「可憐!冗談が過ぎますよ!」
冗談・・・・━━━
そうね。
今なら冗談で済ませられるわね。
暴風雨のような胸を押し殺し、皮肉に笑う。
「あんたが図星指すから悪いんじゃない。あ~くさくさする!逆ナンでもしてこようっと!」
「可憐!」
背中にかけられた声はいつになく震えていたように感じたが、あたしは振り向かない。
「煩いわ。冗談なんでしょ?」
「・・・・・・・。」
「あんたは、もっと悠理を信じてあげなさい。あの子、そんな器用じゃないんだから。」
それからのあたしたちは何もなかったかのように振る舞い、そして時が緩やかに過ぎていった。
6人揃って大学を一年休学し、世界中を旅して回ったり、魅録がチチと再会したけれど結局上手くいかず、本当の別れを迎えたり。
野梨子に二度目の恋が訪れたり、と様々な出来事があった。
━━━卒業後、結婚します。
はにかむ悠理の肩を抱き、そう宣言したのは半年前。
あたしの恋はそこで終着駅を迎えた。
それなのに………………
今日、悠理の口から告げられた事実はあたしを再び打ちのめした。
━━━えへへ。妊娠してるんだ。そろそろ三ヶ月だって。
ああ、彼らの絆はもう誰にも断ち切ることが出来ない。
解っていたけれど、
解っていたのだけれど━━━
ノンアルコールなんて柄じゃない飲み物を口にする悠理を、愛しさ全開で見つめる清四郎。
二人が育んできた愛はあたしの邪な思いをものの見事に打ち砕いてくれた。
むしろ感謝すべきことなのだ。
不毛な恋からの解放を。
彼女の分も酒を飲み、すっかり意識朦朧となったあたしを美童がタクシーに乗せる。
彼の大人っぽい香水が心を落ち着かせ、らしくもない。
つい甘えてしまった。
━━━朝まで一緒に居て?
・
・
「は………ぁ………」
二度目のセックスは涙が零れるほど優しかった。
それほど多くない経験が霞むほど、彼は巧みだ。
「可憐。」
「………何?」
「僕と結婚しよう。」
「………………………え?」
何の冗談かと見上げれば、ブルーの瞳が感情を表すかのように濃くなっていた。
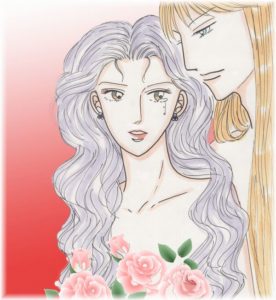
「僕、可憐がいいんだ。お姫様のように愛してあげるから、イエスと言って?」
嗚呼………そんな。
彼がそんなにもあたしの事を考えてくれていたなんて。
それなのに、あたしは彼の身体を利用した。
彼の優しさを、ものの見事に利用したのだ。
「ダメ………ダメよ。あたしなんて………こんな馬鹿な女なんてダメよ。美童。」
「君がバカなことくらい10年も前から知ってるよ。だけど、もうフラフラさせてあげない。どうか、僕のものになってください。」
震える唇を奪われ、どんな言葉も口に出来ない。
「可憐。昔から君は………………僕の可愛いお姫様だったよ。」
これは夢?
いいえ、違う。
頭にこびりついていたはずの清四郎の声が、霧のように消えていく。
あたしは羨ましかっただけなのか。
あれほど愛される悠理が。
あれほど愛せる清四郎が。
金髪の貴公子は望んだものを与えてくれるだろうか。
いいえ。
たとえそうじゃなくても、既に心は彼へと傾き始めた。
ゆっくりと、温もりを帯びながら。
「美童。」
「ん?」
「あたしの王子様になってくれる?」
「もちろん。何なら白馬にだって乗ってあげるよ。」
「ふふ。楽しみにしてるわ。」
苦しみに満ちた想いが引き波のように去り、代わりに聞こえてきたのは祝福の鐘。
二日後の結婚式。
あたしはきっと、誰よりも二人を祝福できるだろう。
