夜風が強い。
連日の雨はおさまったが、日を追うごとに寒くなってきている。
もう、すぐそこにまで冬が訪れていると判り、悠理は小さく肩を竦めた。
今日は酒を飲む気になれず、夕飯の後は魅録の冒険話に耳を傾けていた。
何でもこの男、時として都を離れ、この国の隅から隅まで旅していると云う。
いつか海を渡り異国の地を踏みたいと大望を抱いているが、悠理にとってその野心は到底理解出来ぬもの。
海の向こう?
そんなところは安全なのか?
いくら力のある妖狐とて、家族の居ない地を覗いてみたいとは思えない。
何かあったらどうするというんだ。
手立てなど思いつかないぞ?
「具合、どうだ?」
「…………うん、今日はマシ。」
「まさかとは思うが、腹に子が居る………なんてことないよな?」
顔色の悪い悠理を気遣う男は、躊躇いがちにそう切り出した。
「………居たら、追い出す?」
「莫迦言え!相手の男はどうした?ちゃんと産婆に診てもらわなきゃダメだろう?」
「………冗談だよ。子供なんて………」
居ない────
そう言おうとしたが、声にならない。
あの男の………清四郎の血を引く我が子を一瞬でも無き者として扱うのは不可能だった。
ここには小さい命が宿っていて、それは二人が愛し合った末、授かったもの。
何度も何度も注ぎ込まれた清四郎の想いが実を結んだ、奇跡の結果だった。
ホロホロとこぼれ落ちる涙に、悠理は気付かない。
真っ先に気付いたのは目の前の男だ。
「悠理…………話を聞かせてくれないか。俺ならきっと力になれるから。」
「だって………あたいは………」
「なんなら夫婦になってもいい。おまえの面倒くらい、俺がみてやる。」
抱きしめられたと気付いたのは数瞬あとのこと。
清四郎の高貴な香りとは違い、自分とよく似た匂いのする男に、悠理は思わず身を預けてしまった。
いつもの調子が出ない。
それは寂しさ故のことなのか───?
「魅録…………子は確かに居るんだ。相手が誰とは言えないけど……」
囁くような告白を魅録は頷くことで受け入れる。
相手はよほどの身分なのだろう。
悠理の戸惑いも理解出来るが、このままではいけない。
「騙されたのか?……いや、違うな。もしや、相手が死んじまったとか?」
「違う、生きてるよ!………騙されてもいない。あいつとあたいは………愛し合って………」
身重の女を興奮させてしまった事を、男は恥じた。
胸の中で今にも啜り泣きそうな悠理の頭を、つい子供をあやすようにヨシヨシと撫でる。
「悪かった………よっぽどイイ男なんだな、そいつぁ。」
「うん………この世で一等、イイ男さ。」
複雑な思いに駆られる返答だったが、魅録は聞き流す。
にしてもなぜ、子まで成した女を一人にしたのだ。
こんなにも美しい女を野に放ったままにするなんて………信じられない。
(ったく、不甲斐ない野郎だ)
彼は胸の中だけで毒づいた。
「会いたいのか?」
確信的な質問に悠理も素直に答えるほかない。
こくんと肯定すれば、魅録の腕が少しだけ緩んだ。
「…………会わせてやるよ。それで踏ん切りをつけな。万が一、報われなかったら俺を旦那にすればいい。」
「そんな………会ったばっかじゃないか………迷惑だろ?」
「いいってことよ。おまえさんを招き入れてから、薄々感じていた気がするんだ。こうなることを────」
まるで昔からの知り合いのような親しげな目。
身だけでなく、心までをも預けたくなる包容感に悠理はようやく口元を上げた。
そこへ………
「夜分に邪魔するぜ!魅録。」
粗末な木の扉に鍵などかかっているはずもない。
建て付けの悪さがありありと分かる音を立て、あけすけに登場した男は、頭に巻いた手ぬぐいを取ると、人懐っこい笑みの中に緊張を隠したまま、声をかけてきた。
「宵丸のおっさんか。こんな夜更けになんだ!?びっくりするじゃねぇか。」
「今日はちと聞きてぇことがあってな。おまえさんの記憶が必要なんだ。」
食い気味に話す40そこそこの男。
悠理は魅録の腕からそっと離れ、着物の裾を整えた。
「………てか、客人か?なんだなんだ?女じゃねぇか。」
露骨な興味を示す男に、魅録が慌てて悠理を隠す。
もちろん既に手遅れであったが、どうしてもそうせねばならぬと思った。
この美しい女を、他の男に見せたくない。
立ち昇る独占欲を抑え込めず、魅録は
初めて抱く感情に驚かされた。
「宵丸。目当ての男は居たんですか?」
想像していなかった事態に、すっかり動きを止める小柄な男。宵丸という名の通り、真っ黒な目を瞬かせる。
その後ろから、乗り出すように現れた見目麗しき貴人。
その姿を見た瞬間、魅録はハッと息をのんだ。
どこからどう見ても、“やんごとなき身分”の男────
気品ある顔立ちに相応しき装束は、下々の者には到底手の届かぬ絹衣であった。
装飾こそ少ないものの、高貴な立場を感じさせる。
「おっと……悪うございました。どうぞ、ささ、どうぞ、中へ。むさくるしい場所ですが………」
窄笠を取り外した男は、より一層気高く見えた。
魅録が突然の珍客に唖然としていると、その背中から恐る恐る顔を覗かせた悠理は相手を見てこの上なく目を見開いた。

「せ……清四郎……?」
たった5日。
たった5日しか経っていないのに、もはや数年会っていないかのような感覚にとらわれる。
忘れるはずもないその凛々しい顔、逞しい体。
何度も睦み合い、男の体温を知った。
得たことのない快楽と深い愛を与えられ、溺れるように繋がった。
永遠(とわ)を約束したような幸せを味わった。
「まさか………悠理!?何故、ここに?里へ帰ったのでは?」
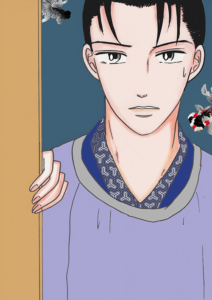
お互いが乗り出し、視線を交わす。
手が震え、名を呼ぶ声も掠れ、背筋が痙攣する。
「なんだ、知り合いですかい?」
宵丸が二人を不思議そうに見比べていると、魅録の苦しげな顔が目に飛び込んできた。
まるで見たくないものを見ているかのような苦渋の表情。
それは彼の鋭い直感が災いしたとも言える。
「清四郎………ほんとに?……夢じゃない?」
「夢なら………これが夢なら、私はもう……目を覚ましたくない。」
同時に駆け出した二人が、土間の真ん中で抱き合う姿を、今や観客と成り下がった男たちはただ呆然と見つめていた。
「今から、貴女を里まで迎えにいくつもりだったんです。あの時の覚悟など、全くの無意味だ。もう、一刻も離れていたくない。どんなことをしても手に入れたくて………」
「あたいは……あと一度だけ会えたらって!里に帰ろうと思ったけど、帰れなくて……清四郎に一目会いたくて……そしたら、二度と会えなくても……我慢するつもりだったんだ。」
人目など気にもせず、この美しい男と女は愛を伝え合う。
このまま放っておけば、場所も考えずにまぐわい始めるのではと思うほど、互いに固く抱きしめ合っていた。
「そんな悲愴な覚悟は必要ありませんよ。もう………二度と離しませんから。」
「でも………」
涙をすくう指先に清四郎は精一杯の優しさを乗せる。
美しい目が濡れているのは切ないとばかりに。
「“妻問い”も何もしていませんが、どうか私の屋敷へ来てください。たとえ誰からどんな誹りを受けようとも絶対に幸せにします。」
「清四郎………」
真剣な瞳から導き出される男の本音に、悠理の心はグラグラと揺れた。
このまま彼の望む通り、屋敷へ出向き、愛される存在で居てもよいのか?
子を産み、妾として清四郎の側に居ることは、確かにこの上ない幸せだ。
ただ─────もし、妖狐とバレたら、清四郎の立場はどうなる?
生まれてきた子供は?
正妻などもちろん望んではいないが、他の女の所へ通う清四郎を黙って見過ごせるのか?
悠理は白檀が香る胸の中で、必死に考えた。
考える事は苦手なのに、今はその課題から逃げられない。
「おい。ちょっといいか?」
そこへ魅録が訝しげに口を挟んだ。
二人はハッとそちらへ向き直る。
「あんたたちが妹背に近い仲ってのは充分解った。俺たちなんかが口も聞けないような立場だって事もな。………でもなんでもっと早く悠理を連れ行かなかったんだ?子を孕んでいる事は知らなかったのか?」
「───── 子?」
寝耳に水な言葉に、清四郎は愛しい女の顔をマジマジと見つめる。
それに対し、眉を下げ視線を背ける悠理。
もう言い逃れなど出来ない。
「本当ですか?………ここに私の子が?」
着物の上からそっと触れてきた温かい手に、痺れるような歓びを感じ、コクンと頷く。
その大きな手は夜の記憶をもよみがえらせる力があった。
「しかしまだ、そんなに時は経っていないはず………」
「あたいたちは……そういうの直ぐに判るんだ。従姉のねぇちゃんも、契った次の日に判ったって言ってたし。でも、こんなつもりじゃなかったんだ………ごめん。」
何を謝る必要がある────!
清四郎は感極まる心を押し殺したりしなかった。
悠理を強く抱き締め、何度も“愛しい”と呟く。
その喜びに満ちた光景を、男二人は照れながらも見つめ、仕方ねぇなぁと頭を掻いた。
どんな事情があるにしろ、彼らは深く想い合っている。
余所者の入る隙間はなさそうだ。
「宵丸、ありがとう。………取り敢えず、私の目的は果たせました。謝礼はいかほどでも。」
「へ、へぇ、有り難きお話で。ではこの魅録を側に置いては如何でしょう?何かと役に立ちますぜ?」
「おい、おっさん!何、勝手に決めて…………」
「いいから、言うことを聞いとけ!おまえもいい年だ。いつまでもフラフラしてられねぇだろうが。」
グッと黙り込む魅録を見て、清四郎はふむと顎を一撫でした。
見た目もそうだが、なかなか気骨のある男のようだ。
立場を省みず、堂々と意見するその姿勢も気に入った。
「構いませんよ。我が屋敷へと招きましょう。どうやら悠理がお世話になったことですし。」
「え……本気で?」
「もちろん。働き次第では出世する事も可能ですから。」
突然の話に目を白黒させた魅録は、目の前の男の度量を知る。
──────はは、かなわねぇな。
貴族も十人十色だが、ここまで懐深い男は初めてだった。
「解った、世話んなるぜ。これからは悠理の守り人として働かせてもらうよ。もちろんやるからにゃ、命を賭けるさ。」
「それは願ったり。………しかし、彼女に懸想することは許しませんよ。」
全てを見透かした上で側にいることを許可した清四郎。
悠理の身も心も自分のものしたという自信が、彼に余裕を抱かせたのだ。
「悠理………望むものがあれば何なりと。貴女が欲する物は全て、私が与えます。」
「あたいは………清四郎だけが欲しい。それ以外は別に………」
「おやおや。どの口が言うんでしょうね?食いしん坊姫。」
「め、飯は当然だろ!?」
「ええ。なんなりと。」
更ける夜道を、宵丸を除く三人は馬に乗り屋敷へと向かう。
そんな彼らを木陰から見つめる一人の間者。
闇に溶け込んだその男は、想像もし得なかった情報に、思わずほくそ笑んだ。
「これは思った以上の手柄になりそうだな。」
波乱はまだ先の話。
馬の背に乗る悠理は清四郎の胸に包まれながら、この上ない幸せを感じていた。
